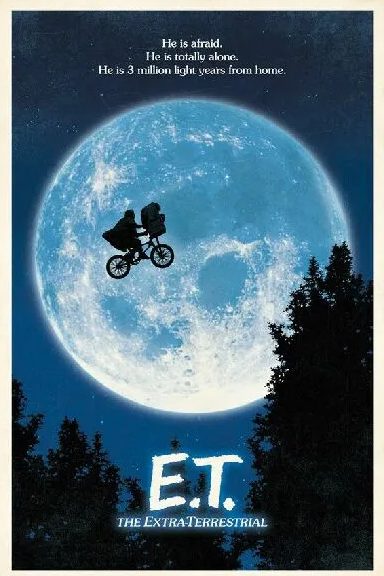40年以上前に生まれた物語が、いま、なぜこんなにも心に刺さるのか。
それは、『E.T.』が描くのが「宇宙人との出会い」ではなく、
「自分の中にある、誰にも言えなかった寂しさ」だからだ。
夜、誰かとつながりたかった。
けれど、家族にも友だちにも届かない声があった。
そんな声を、空から来た小さな手がそっと掬い上げてくれた。
これは、子どもだったあなたへ贈る物語。
そして、今もまだ、誰にも話せない気持ちを抱えているすべての人に——
『E.T.』は、あの光の先に“帰る場所”があることを教えてくれる。
この記事を読むとわかること
- 映画『E.T.』が40年以上経った今でも愛され続ける理由
- 子どもの視点で描かれた独特な演出の意味
- エリオットとE.T.の“共鳴”が象徴する心のつながり
- スピルバーグ監督の原体験が物語に与えた影響
- 音楽と映像が生み出す「心の飛翔」の瞬間
- 別れのシーンが教えてくれる、愛と手放しの哲学
- 1980年代に起きた“E.T.ブーム”の社会的背景
- 大人になった今だからこそ観て感じる、新たな感動
はじめに|なぜ今、E.T.なのか?
1982年に公開された映画『E.T.』──
それは、単なるSF映画でもなければ、宇宙人との友情物語でもない。
あの物語には、“今なお誰もが持ち続けている孤独”が、確かに映っている。
SNSに溢れる「わかってほしい」という叫び。
大人になることで置き去りにしてきた“心の声”を、
あの小さな異星人が、今もどこかで聞いてくれている気がするのです。
だから私は思う。
“今だからこそ、もう一度E.T.を観てほしい”と。
子供の視点で描かれる世界のリアル
この映画で最も特異なのは、カメラが一貫して「子どもの目線」で描かれていること。
大人たちは物語の背景に押しやられ、視界から切り取られる。
大人の顔はほとんど映らず、物語はまるで「子どもたちの世界」だけで完結しているように感じる。
それは、現実において子どもたちが感じている“見えない隔たり”の象徴。
大人は何もわかってくれない、何も見ていない──
その絶望のなかで、エリオットは“本当に心が通じる存在”に出会うのです。
孤独な少年と異星人の“共鳴”
E.T.とエリオットの関係性は、単なる友情ではありません。
彼らはお互いの“穴”を埋めるようにして存在し合う。
例えば、E.T.がビールを飲めば、エリオットが酔う。
E.T.が傷つけば、エリオットも苦しむ。
この“共鳴”は、誰かと心を通わせるとはどういうことか──
その最も美しく、痛みを伴うかたちで描かれているのです。
エリオットにとってE.T.は「宇宙から来た友達」ではなく、
**“自分の孤独が形を持った存在”**だったのかもしれません。
スピルバーグの原風景としてのE.T.
監督スティーブン・スピルバーグの両親は、彼が幼いころに離婚しています。
『E.T.』における“父の不在”というテーマは、彼の私的体験に深く根ざしています。
エリオットの家庭には、常に“空席”がある。
母親の不安も、兄との距離も、その中心には不在の父という重力がある。
そこに突如現れるE.T.という“異物”は、家庭の中にぽっかり空いた穴を埋める存在になる。
つまりこの映画は、監督自身の“癒えなかった傷”の代弁でもあるのです。
音楽と映像が導く“心の飛翔”
誰しも一度は目にしたことがあるでしょう。
──あの、自転車が月を背に空を舞うシーンを。
エリオットがE.T.を乗せて逃げる途中、森の中で自転車が空を飛ぶ。
その瞬間、ジョン・ウィリアムズの壮麗なテーマ曲が流れ出す。
音楽と映像がシンクロし、心が身体を離れていく。
それは、ただのファンタジー描写ではなく、
**「重力のある日常から、感情が解き放たれる瞬間」**です。
あの一瞬に、私たちは“自由”を見て、“希望”を知る。
“映画って、こんなにも人の心を飛ばせるんだ”と、初めて知った人も多いはずです。
別れの痛みと再生の希望
物語の終盤、E.T.は故郷へと帰ることを選びます。
その瞬間、エリオットの心には“失うことの痛み”が訪れます。
「僕、ずっと忘れないよ。」
このセリフは、子どもが初めて経験する“別れ”の痛みであり、
“愛すること”と“手放すこと”がセットであるという、残酷な真実でもある。
でもその痛みこそが、成長の証でもある。
E.T.が帰る=欠けることで、エリオットの心に初めて“自立”が宿る。
別れは終わりではなく、“再生の始まり”なのです。
社会現象としてのE.T.ブーム
1982年の公開当時、E.T.は世界的な社会現象となりました。
日本でも“E.T.、オウチ、デンワ”のセリフは子どもたちの流行語となり、
グッズ、絵本、ビデオテープ、BMX自転車──
日常がE.T.で彩られた時代がありました。
これは、単に商業的な成功ではありません。
「E.T.」という物語が、多くの子どもたちの“拠り所”になっていた証なのです。
大人がわかってくれない。
友だちもうまくできない。
そんな子どもたちの空白に、E.T.という存在はそっと寄り添ってくれた。
『E.T.』が教えてくれること|愛することと、手放すこと
私たちは、いつも“永遠”を求めてしまう。
大切なものを、ずっと傍に置いておきたいと願ってしまう。
でも『E.T.』は、こう問いかける。
「その愛は、相手を自由にしているか?」と。
愛することは、握りしめることじゃない。
触れた指先を、そっと離すことでもある。
別れを受け入れること。
その痛みのなかで、初めて人は本当の意味で“愛を知る”のかもしれない。
まとめ|『E.T.』という物語が灯すもの
『E.T.』を初めて観たのは、私が小学2年生のときだった。
父がいなくなった後、テレビの向こうで“宇宙人と子ども”が手を取り合っていた。
私はその夜、なぜか泣きながら眠った。
言葉にならない感情を、E.T.が代わりに受け止めてくれたような気がした。
この映画は、誰かと心を通わせたかった“かつての私たち”に贈られた物語。
観るたびに、自分の中の“孤独だった誰か”と再会できる。
そしてこう思うのです。
**「きっとまた、あの光が迎えにきてくれる」**と。
この記事のまとめ
- 『E.T.』は、子どもの視点を通して“孤独”と“再生”を描いた物語である。
- エリオットとE.T.の心の共鳴は、言葉を超えた本当の理解を象徴している。
- スピルバーグ自身の傷が、作品に普遍性と深い感情を与えている。
- 別れの場面が残す“余白”は、私たちの人生の再解釈を促してくれる。
- 『E.T.』はただ懐かしいだけの映画ではなく、今の私たちにこそ必要な一編である。
子どもの頃に置いてきた感情──
あの映画は、それをもう一度抱きしめ直すための光なのかもしれない。